「東京にあるカフェの数は?」こんな一見突飛な質問に戸惑ったことはありませんか?
実はこれ、近年の転職面接でも使われることが増えている「フェルミ推定」という質問形式です。特にコンサル業界や企画職、マーケティング職など、論理的思考や仮説構築力が求められる職種では、高い頻度で登場します。
本記事では、フェルミ推定が面接で使われる理由や企業側の意図、評価される考え方や答え方のコツについて、採用のプロがわかりやすく解説します。転職活動中に備えておきたい「フェルミ推定」の本質を理解し、選考を有利に進めましょう。
フェルミ推定とは
フェルミ推定(フェルミ推論)とは、実際に正確なデータを得ることが難しい問いに対して、いくつかの手がかりや前提をもとに論理的に仮説を立て、短時間で概算する推論方法のことです。
与えられる情報はほとんどなく、自分の知識や常識、仮説から数値を導き出す思考力が問われるため、「論理的思考力」「仮説構築力」「計算力」などが評価される質問形式として、主にコンサルティングファームや外資系企業の面接で頻繁に使われています。
面接で出題されるフェルミ推定の特徴
フェルミ推定は、特定の正解があるわけではありません。重要なのは「どのような前提を置き、どうやって数値を導き出したか」というプロセスのロジックです。
そのため、面接官は最終的な答えよりも、「考え方の筋道」や「柔軟な発想力」「構造化された思考」を見ています。
フェルミ推定のよくある例題(質問例)
面接で実際に出されることのあるフェルミ推定の定番例題には、以下のようなものがあります。
- 日本に猫は何匹いるか?
- 東京都に電柱は何本あるか?
- 渋谷のスタバの1日の売上は?
- 日本にピアノ調律師は何人いるか?
- 日本全国にあるマンホールの総数は?
- 東京都内に走っているタクシーの台数は?
- 日本に存在するパソコンの総数は?
これらの質問に正確な答えを出すことは誰にもできません。しかし、「仮説→分解→計算→概算」という一連の流れを論理的に説明する力を見せることができれば、面接官に好印象を与えることができます。

フェルミ推定のメリットとは?採用担当が注目する3つの理由
メリット1:数字に強い人材かどうかを見極められる
フェルミ推定は、応募者が数字に強いかどうかを判断できる効果的な質問です。
ビジネスにおいては、業種や職種にかかわらず「数字感覚」は必須のスキルです。たとえば営業職であれば、売上目標を達成するために必要なアプローチ件数や成約率など、数値に基づいた行動計画を立てる必要があります。
また、見積書の作成や予算管理など、顧客対応の場でも瞬時に計算や見積もりができる力は大きな武器となります。これは営業だけに限らず、マーケティング、経営企画、技術職などあらゆる部署で求められる能力です。
フェルミ推定によって、数的感覚や数字に対する柔軟な対応力を持っている人材かどうかを見極めることが可能になります。
メリット2:論理的思考力を可視化できる
フェルミ推定は、応募者の論理的思考力を客観的に測る有効な手段です。
たとえば「コミュニケーション能力」などは、企業によって定義や評価基準が曖昧で、面接官ごとの解釈に差が出やすいスキルです。その点、「論理的に考える力」は、ある程度客観的に判断しやすい能力と言えます。
フェルミ推定では、正確な答えを求めているわけではなく、仮説を立て、それを論理的に展開し、納得感のある答えに導けるかどうかが評価ポイントとなります。
このような思考力は、課題解決や意思決定の場面で非常に重宝され、特にコンサル業界や企画系職種では高く評価されます。面接においてフェルミ推定を使うことで、応募者の「考え方の質」を浮き彫りにできるのです。
メリット3:事前準備ができる人材かどうかを見極められる
フェルミ推定の質問を通じて「準備力のある人材かどうか」も判断できます。
フェルミ推定は初見で答えるのが難しいと思われがちですが、実際には頻出のテーマや解法の型が存在し、ある程度の対策が可能です。そのため、面接で問われた際に落ち着いてロジックを構築できるかどうかは、「どれだけ事前に準備してきたか」が大きく影響します。
たとえば、「日本にコンビニはいくつあるか?」「東京に電柱は何本あるか?」といった定番の質問に対して、自分なりのフレームワークで答えを出せる人材は、面接に向けた自主的な準備ができるタイプと判断できます。
このように、フェルミ推定を通じて、単なる知識やセンスだけでなく、目標に向かって準備・行動できるかという姿勢を評価することが可能なのです。結果だけでなくプロセスに注目するフェルミ推定は、「準備力」や「努力できる資質」を見抜くためにも有効な質問形式です。
フェルミ推定は地頭を見極めるのに最適な質問
採用の現場では、履歴書や職務経歴書だけでは判断しきれない「地頭力」や「思考のクセ」を把握するために、フェルミ推定が活用されています。
数字感覚と論理的思考力の両方を見極められるため、特にポテンシャル採用やポジション未経験の候補者を評価する場面で、非常に有効な手法といえるでしょう。
採用担当者が知っておくべきフェルミ推定のデメリット
少し前に地頭力(じあたまりょく)が流行りました。
地頭力の正確な定義はありませんが、その人本来の頭のよさ、問題解決に必要となる考え方のベースとなる能力、問題解決能力の基盤としての基礎的な力といった意味を指します。
もともとフェルミ推定はアメリカのグーグルやマイクロソフトが採用試験で導入していたことから注目され始め、日本でも専門の書籍や問題集が発売されるほど人気を博しました。
しかし、フェルミ推定では確かに高い知能を持っているかどうかを知ることができますが、実務能力とはあまり関係がないことも一部では証明されており、現在のグーグルでは意味がなかったと廃止されています。
フェルミ推定の基本的な解答方法・やり方
例題1:「日本にピアノ調律師は何人いるか?」
- 仮説を立てる(前提を置く)日本の人口は約1億2000万人
- 3世帯に1台はピアノを所有していると仮定 → 約4000万世帯 / 3 = 約1300万台のピアノ
- そのうち定期的に調律されているのは2割 → 1300万 × 0.2 = 260万台
- 調律頻度と作業量を考える
- ピアノの調律は年に1回と仮定
- 調律師1人が1日に3件、年間250日稼働 → 3 × 250 = 750台/年
- 必要な調律師数を計算:260万台 ÷ 750台 ≒ 約3,467人
- 結論:日本にピアノ調律師は約3,500人いると推定できる。
例題2:「東京にあるコンビニの数は?」
- 前提の設定:東京の人口は約1,400万人
- コンビニ1店舗あたり、平均3,000人に1店舗と仮定(地方より密度高め)
- 計算:1,400万人 ÷ 3,000人 ≒ 約4,666店舗
- 結論:東京都内のコンビニ数は約4,500〜5,000店舗と推定できる。(実際のコンビニ数とも大きく乖離していない推論です)
例題3:「渋谷のスターバックス1店舗の1日の売上はいくら?」
- 前提の設定:平均客数:1時間あたり40人 × 12時間営業 = 480人/日
- 平均客単価:600円
- 売上:480人 × 600円 = 288,000円/日
- 結論:渋谷のスタバ1店舗の1日の売上は約28万円と推定できる。
就活性が知っておくべき知識と面接対策
新卒採用の面接においてフェルミ推定について質問する企業はまだ存在します。
圧迫面接として活用する企業もおり、準備しておくに越したことはありません。フェルミ推定は物事の論理的思考力を鍛える意味では有効ですので、勉強の一環だとポジティブに考えてほしいと思います。
コンサルティングファームや外資系企業で質問される傾向にありますが、大手国内メーカー企業でも質問されたり、グループディスカッションのテーマにされることがあります。
営業職でも地頭が求められる仕事もあり、頭がよくないとできない仕事があるのも事実です。資格が必要なケースや、難しい商品知識を覚えるためには記憶力や理解力が高くないとついていけません。
そのため面接の段階で思考能力を判断するためにフェルミ推定を聞くのは合理的な部分もあります。
まとめ
フェルミ推定によるメリットとデメリットをまとめました。
フェルミ推定は論理パズル(ロジックパズル)と並び超難問で社会人でも論理的に回答することが難しい質問ですが、思考の柔軟性を鍛える意味では面白い質問で「勉強になった」と回答する学生もいます。
ロジカルシンキング・計算スピード・ビジネスセンスを鍛える意味でも一度は勉強しておきたい分野ですね。


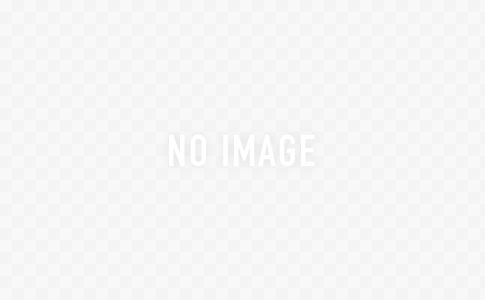






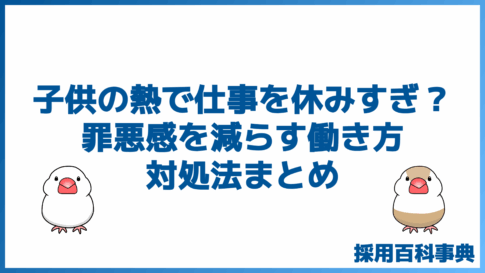

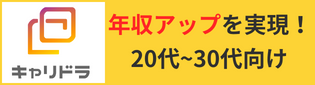


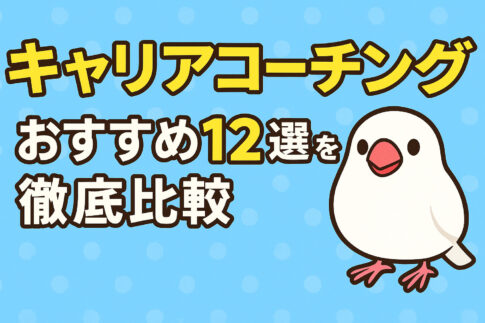
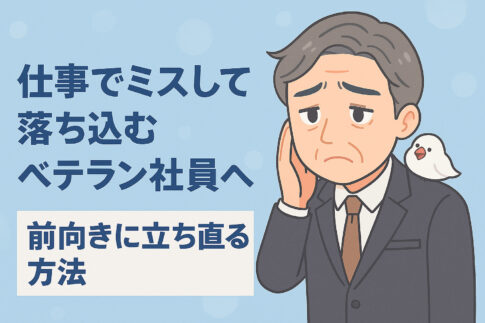
日本トップクラスの転職サイト!正社員求人多数
転職エージェントと求職者をつなぐプラットフォーム
顧客満足度No.1!国内最大級の転職サイト兼転職エージェント
20代・第二新卒専門の転職エージェント