「人材業界はやめとけ」とネットで検索すると、なんJや知恵袋にはネガティブな体験談が多く並びます。長時間労働やノルマの厳しさから「ブラックな業界」というイメージを持つ方も少なくありません。
とはいえ、すべての人材会社が悪いわけではなく、営業経験を活かして大きくキャリアアップできる人や、隠れホワイト企業で安定した働き方を実現している人もいます。
この記事では、転職活動中の方に向けて「やめとけと言われる理由」「向いてる人・向いてない人の特徴」「隠れホワイト企業の見極め方」を現役求人広告代理店が徹底解説します。
人材業界はやめとけと言われる理由
人材業界は「やめとけ」と言われることが少なくありません。その理由は、労働環境や仕事内容、待遇に関する課題が転職市場でも広く知られているからです。
ここでは代表的な4つのポイントを解説します。
長時間労働と高い離職率
人材業界は慢性的に長時間労働になりやすく、早朝の企業訪問や夜遅くまでの求職者対応が日常的に発生します。
昼間は通常業務が優先のため、社内の営業会議、週次会議が業務時間終了後のケースも普通です。雑務は土日にやらないと終わらないといった声もよく聞きます。
土日や夜間に打ち合わせや面談が入るケースもあり、ワークライフバランスを保ちにくいのが実情です。
ノルマ営業が中心になりがちな仕事内容
基本的に人材業界は営業会社が多いです。
人材会社のビジネスモデルは「企業からの売上」であるため、営業活動が必要不可欠です。常に求人企業の新規開拓が必要になるため、営業職にはノルマが設定されます。
営業には毎日・毎週・毎月・四半期の契約数・売上目標が課され、達成できなければ厳しい評価や叱責を受けることも少なくありません。
コンサルタントやキャリアアドバイザーの場合でも、求人企業への紹介数や決定人数といったノルマが設定されます。ノルマがないのは営業事務や経理などのバックオフィス職くらいです。
求職者支援のやりがいはあるものの、退職理由には「数字に追われて精神的に消耗した」という声が多いのも事実です。
給与のギャップ(求人広告との乖離)
求人広告では「年収〇〇万円以上可」「インセンティブ制度あり」といった魅力的な条件が並びますが、実際にはそこまで給与はもらえないケースがほとんどです。
求人広告の年収例はトップ営業マンのケースが多いため、ほぼ嘘です。単純に給与だけで比較すると不動産業界や金融業界のほうが高いです。その分、営業職のプレッシャーが高い業界になりますが…。
人材業界の場合、企業にもよりますが、中堅~大手企業のトップ営業マンでも年収1000万には届きません(リクルート別格)。さらに、固定残業代制度を採用している企業も多く、実際の労働時間に見合わない報酬しか得られないケースもあります。
福利厚生も大手企業に比べると十分ではない場合が多く、「求人票と現実のギャップ」に失望して早期退職する人も少なくありません。
ネット上の口コミ(なんJ・知恵袋の声)
実際に働いた人の体験談は、なんJや知恵袋などネット掲示板にも数多く投稿されています。「数字に追われて心身ともに疲れ果てた」「入社前の説明と全然違った」「ブラック体質が当たり前」など、辛辣な意見が目立ちます。
一方で「成果を出せば20代で部長職」「前向きな性格の人間が多く活気がある」といったポジティブな声もあり、業界全体の二極化が浮き彫りになっています。これらの口コミは信憑性の差はあれど、転職活動を検討するうえで参考にすべきリアルな情報源です。
まとめ:総合的に離職率が高い
上記の要因が組み合わさって離職率が高く(とくに営業職)、「3年以内に半数以上が辞める」企業も存在します。
転職市場でも「短期離職者が多い業界」として認知されており、求職者にとってリスクのある選択肢とみなされやすいです。

人材業界の主な分類と特徴
人材業界は「人と仕事をつなぐ」という共通点を持ちながらも、提供するサービスやビジネスモデルによって複数の業種に分かれています。
それぞれの特徴を理解することで、転職活動時にどの領域が自分に合っているのかを判断しやすくなります。
人材紹介(有料職業紹介事業)
企業と求職者をマッチングし、採用が成立した際に「成果報酬」を得るビジネスモデルです。
キャリアアドバイザーや法人営業(リクルーティングアドバイザー)といった職種が中心で、看護師・介護職・建設業・エンジニアなど、専門職に特化した人材紹介会社も多いです。
人材業界の中では、高収入を得やすい業態でもあり、人材業界から採用担当へキャリアチェンジしやすい業界でもあります。
人材派遣(一般派遣・特定派遣)
派遣スタッフを自社で雇用し、取引先企業に一定期間派遣するモデルです。雇用主は派遣会社であり、労働条件の整備や契約管理が重要な業務になります。
短期・単発の派遣や長期派遣など多様な形態があり、労務管理能力が求められます。求職者対応よりも「派遣スタッフの就業フォロー」が比重を占めるため、営業職だけでなく労務管理職の活躍も目立ちます。
アウトソーシング・業務請負
コールセンターや製造ライン、IT開発プロジェクトなどを一括して請け負い、自社のスタッフで運営するモデルです。
人材派遣に近い要素を持ちながらも、契約形態は「成果物納品」や「業務委託」となるため、マネジメント力や組織運営能力が問われます。BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)などの形で大手企業のバックオフィス業務を代行するケースも増えています。
求人広告・求人メディア運営
求人サイトを通じて広告掲載料を得るビジネスモデルです。
代表例としてリクナビ・マイナビ・Indeedなどがあります。営業職は企業に求人広告を提案する役割を担い、クリエイティブ部門が広告制作を行うのが一般的です。
売上は安定している一方で、広告効果を数字で示す必要があり、マーケティングやデータ分析力も求められます。
社員研修・組織開発・HRテック
採用代行や社員研修、人事制度設計や組織開発、従業員の給与計算ツールや勤怠管理システムも人材業界に含まれます。
AIマッチングやタレントマネジメントシステムなどを開発するIT系人材サービス会社も増えており、従来の「労働集約型」から「テクノロジー活用型」へ移行しているのが特徴です。
人材業界というより「人材サービスを提供している企業」になるため、中途採用メンバーで構成された落ち着いた会社も多いです。
人事課題を解決するコンサルタントとして働けるため、専門性を高めたい人に向いています。

人材業界の主な職種・求人一覧
人材業界といっても、その仕事内容は一律ではなく、企業によって担当する職種や役割が大きく異なります。ここでは、転職を考える求職者が知っておくべき主要な職種を紹介します。
営業職(すべて)
人材業界で最も求人数が多い職種です。
未経験から入社でき、採用枠も多いです。求人広告、人材紹介、人材派遣、その他含めて全ての会社に営業職はあり、会社の屋台骨を支える職業と言っていいでしょう。
ノルマに追われる日々ですが、達成すればインセンティブもあり、やりがいがあります。採用が上手くいけばクライアントに直接感謝される点も、やりがいです。
一方で、人材業界はレッドオーシャン市場かつ無形サービスのため、営業難易度は高いです。差別化が難しいこともあり「やめとけ」と言われる最大の理由です。
キャリアアドバイザー(人材紹介)
求職者に寄り添い、希望条件に合った最適な求人を提案する職種です。
キャリアプランをヒアリングしながら面接対策や履歴書の添削なども行い、転職活動を二人三脚でサポートします。営業色よりも「対人コミュニケーション力」が重視され、相談業務にやりがいを感じる人に向いています。
リクルーティングアドバイザー(人材紹介)
企業側を担当し、採用ニーズをヒアリングして適切な人材を提案する営業職です。
新規開拓や既存企業のフォローが中心で、数字目標が明確に設定されることが多いのが特徴です。法人営業経験がある人はスキルを活かしやすく、成果に応じて高収入を狙えるポジションでもあります。
人材派遣コーディネーター(人材派遣)
派遣スタッフと企業の間に入り、マッチングや労務管理を行う職種です。
就業後のフォローや勤務条件の調整なども担当し、現場でのトラブル対応力が求められます。求職者との関わりが長期にわたるため、人との信頼関係を築ける人に適しています。
人材コンサルタント(その他)
企業の採用課題を包括的に解決する役割を担う職種です(営業職の別名の場合も)。
採用戦略の立案や人事制度の提案、研修企画などに携わる場合もあり、よりコンサルティング色が強いのが特徴です。経験や実績が評価されやすく、スキルアップ次第では大手企業やコンサルティング会社への転職にもつながります。
エンジニア(求人広告)
求人サイト運営会社など一部の企業のみ求人募集しており、求人数は多くありません。人材派遣や人材紹介会社にとってエンジニアは不要な職種なため、社内に一人もいないことが大半です。
営業部と違い、ノルマに追われることもありません。大手ポータルサイトの運営に携われることは今後のキャリアステップとして貴重な経験になるでしょう。
注意点として、人材会社のエンジニアは社内ヒエラルキーが低いことが多いため、新卒入社の無知なWebディレクターから無茶な納期、意味不明な指示をされることがあります。論理的に回答しても「それを頑張ってやるのがあなたの仕事でしょ?」と無茶ぶりされることも…。
デザイナー・広告制作(求人広告)
求人サイト運営会社など一部の企業のみ求人募集しており、求人数は多くありません。人材派遣や人材紹介会社にとってデザイナー・広告制作は不要な職種なため、社内に一人もいないことが大半です。
求人広告のアイキャッチ画像、採用ホームページ制作、採用ランディングページ制作が主な仕事です。会社によってはハローワークの職業訓練校出身(実務未経験)でも受け入れてくれますが、給与は高くありません。
そのため3年辛抱して働き、スキルと経験を身につけながら、年収が上がらなければキャリアアップとして別の会社に転職していくのが賢い選択です。

人材業界に「向いてる人」の特徴
人材業界は「やめとけ」と言われる一方で、適性のある人にとってはキャリアアップのチャンスが多い業界です。特に営業経験や成果主義に前向きな人は高く評価されやすく、20代・30代で一気に年収や役職を上げることも可能です。
ここでは、転職活動中に「自分は向いているのか?」を判断するためのポイントを解説します。
前向きでこまかいことを気にしない人
人材業界では 前向きで細かいことを気にしすぎない人が向いています。
この業界では、営業活動や求職者対応のなかでトラブルが頻繁に起こります。例えば、上司からの叱責、求職者の突然の辞退や、企業からの厳しいフィードバックなど、精神的に揺さぶられる場面は日常茶飯事です。そんなときに「いちいち落ち込まず、気持ちを切り替えられる人」は成果を出しやすい傾向があります。
また、成果主義の文化が根付いているため、短期的に結果が出ない時期があっても、前向きに行動を続けられる人は高い評価を得やすいです。逆に、失敗や小さなミスを長く引きずるタイプの人は、プレッシャーに押しつぶされやすく、業界に馴染みにくいといえるでしょう。
人材業界においては「細かいことを気にしすぎず、良い意味で楽観的な性格」が長く活躍するための重要な資質です。

営業経験を活かしたい人(特に法人営業出身者)
法人営業の経験がある人は人材業界で即戦力として活躍できます。
人材業界の中心業務は「企業から求人を獲得し、求職者を紹介する」営業活動であり、提案力・折衝力・関係構築力といった法人営業のスキルはそのまま活かせます。
特に無形商材の営業経験を持つ人は、人材紹介や派遣サービスと親和性が高く、転職後すぐに成果を上げやすい傾向があります。
さらに、人材業界ではクライアントだけでなく求職者との信頼関係も重要なため、営業スキルに「ヒアリング力」や「課題解決力」を加えて発揮できる人は長期的に成功しやすいでしょう。
成果主義にやりがいを感じる人
成果主義を前向きに受け止められる人は人材業界に向いています。
人材業界は目標数字が明確で、結果がそのまま評価や報酬に直結します。インセンティブ制度を導入している企業も多く、成果を出せば20代でも年収600万〜800万円に届くことも珍しくありません。
一方で、数字を追うことにストレスを感じる人には厳しい環境です。しかし「頑張った分だけ評価されたい」「結果を出すほど収入を伸ばしたい」と考える人にとっては、やりがいを感じやすい業界といえるでしょう。
短期間でマネジメントや年収アップを狙いたい人
早くマネジメント経験を積みたい人や短期間で年収アップを狙う人に、人材業界は最適です。
この業界は離職率が高い分、ポジションの空きが出やすく、成果を出した人材は若くしてチームリーダーやマネージャーに抜擢されるケースが多くあります。他業界に比べて昇進スピードが早いため、キャリアアップの即効性が期待できます。
さらに、マネジメント経験や高い営業実績を積んだ人材は、他業界へ転職する際にも評価されやすく、市場価値を大きく高めることが可能です。短期間で収入や役職を伸ばしたい人にとって、人材業界は挑戦する価値があるフィールドといえるでしょう。
人材業界に「向いてない人」の特徴
人材業界は、成果主義やスピード感を好む人には向いていますが、すべての人にとって働きやすい環境ではありません。
特に転職を検討している人は、自分の価値観と人材業界の働き方が合っているかどうかを冷静に見極める必要があります。ここでは「向いていない人」の代表的な特徴を解説します。
ワークライフバランスを重視する人
プライベートの時間を大切にしたい人には人材業界は向いていません。
この業界では、企業との商談や求職者面談が夜間や休日に入ることが多く、労働時間が長くなりやすいのが実情です。さらにノルマ達成のために休日出勤や残業が常態化している企業もあり、ワークライフバランスを最優先に働きたい人にとっては厳しい環境となるでしょう。
安定志向で環境変化に弱い人
安定志向の強い人は人材業界に馴染みにくいです。
人材業界は景気や採用市場の動向に左右されやすく、売上や個人の成果も変動しやすいのが特徴です。さらに、組織体制や評価制度が短期間で変わることも多いため、環境変化に柔軟に対応できない人はストレスを抱えやすいでしょう。
じっくり専門性を磨きたい人
職種にもよりますが、3年も働ければ「飽きる」人が多いです。
毎日同じことの繰り返すになるため「アルバイト領域の広告営業を3年やって仕事の魅力が無くなった」「求人広告の画像ばかりで制作していて、今以上のスキルが身につかない」「開発といっても保守運用だけで「やりがい」がない」といった声があります。
業界全体で20代が多いのも上記が理由です。
人材業界の仕事は営業活動やマッチング業務が中心で、幅広い案件をスピード感を持って対応することが求められます。そのため専門性を高めたい人には物足りなさを感じやすいでしょう。評価基準も「成果」が中心となるため、専門スキルの積み上げよりも営業力や数字管理の方が重視されます。
人材業界はオワコン?将来性とキャリアへの影響
近年「人材業界はオワコンなのでは?」という声を耳にすることがあります。実際、従来型のビジネスモデルには限界が見え始めていますが、その一方で成長している領域も存在します。
ここでは業界の将来性と、転職者のキャリア形成への影響について解説します。
縮小している分野(求人広告モデルなど)
従来の紙媒体や求人広告モデルは、近年大きく縮小しています。
インターネットやSNSの普及により、企業が自社で採用サイトを構築したり、ダイレクトリクルーティングを活用したりするケースが増え、広告型人材ビジネスの市場規模は停滞傾向です。
また、求人検索エンジン(Indeedや求人ボックスなど)が普及したことで、従来の「求人広告を販売するだけ」の営業スタイルは競争力を失いつつあります。その結果、求人広告分野に依存する人材会社は淘汰が進み、「オワコン」と言われる背景となっています。

成長分野(IT人材・外国人採用・専門職紹介)
一方で、人材業界全体は成長しており、市場規模は10兆円まで伸びています。
特にエンジニアや看護・介護・医療系の紹介は需要が急増しており、専門性を持つ人材会社は成長を続けています。さらに、少子高齢化による労働人口減少を背景に、外国人採用支援も拡大しています。
介護・医療や、建設・土木などの現場を中心に、外国人材の紹介や派遣は今後さらに重要な分野になるでしょう。また、医療・看護師・薬剤師などの専門職紹介は景気に左右されにくく、安定した需要があります。これらの成長領域では、むしろ「人材業界の将来性は高い」と言えます。

人材業界での経験は他業界で評価されやすい
人材業界での経験は、他業界でも高く評価されやすいのが特徴です。
理由は、営業力・ヒアリング力・マッチング力といった汎用的なスキルを短期間で習得できるためです。特に法人営業やコンサルティング営業に近い経験は、IT、金融、不動産など「成果主義の営業職」で強みを発揮できます。
一方で、「人材業界しか経験がない」と思われるリスクもあるため、転職者は在籍中にマネジメント経験やデータ分析力を身につけておくことが重要です。こうしたスキルがあれば、将来は人材業界以外の業界でも即戦力として通用するキャリアを築くことができます。
人材業界への転職活動の注意点
人材業界への転職を考える際は、求人票の表現や企業の実態を鵜呑みにするのは危険です。
業界特有の言い回しや実態と乖離した条件も多いため、しっかりと確認・調査をしてから応募することが重要です。ここでは転職活動で特に注意すべきポイントを解説します。
求人票の「営業職なのにコンサルタント」といった表現に注意
人材業界の求人では「キャリアコンサルタント」「リクルーティングアドバイザー」「カスタマーサクセス」などの肩書きがよく使われています。
しかし実態は「法人営業」と変わらないケースが多く、ノルマ達成を前提とした営業活動が中心です。華やかな職種名に惑わされず、仕事内容の欄に「新規開拓」「目標数字」「企業への営業活動」といった記載があるかを必ず確認しましょう。
肩書きよりも「業務内容のリアル」を見ることが、転職後のミスマッチを防ぐポイントです。

離職率や残業時間の実態を確認する方法(口コミ・面談での質問)
求人票に記載される「平均残業時間:20時間以内」「定着率90%以上」といった数字は、必ずしも事実ではありません(かなり古い数字や特定部署だけの数値だけのケースがあります)。
そのため、転職活動中は口コミサイト(オープンワークや転職会議など)を通じてリアルな声を調べることが重要です。
さらに面接時には「1日のスケジュール」や「繁忙期の残業時間」「入社1〜3年目の離職率」などを具体的に質問するのがおすすめです。数字を明言できない企業は、働き方に不透明さがあると判断できます。
応募前に「紹介・派遣・アウトソーシング」など事業形態を見極める
同じ人材業界でも、人材紹介・派遣・アウトソーシング・求人広告など事業形態によって仕事内容は大きく異なります。
例えば、人材紹介は成果報酬型で「成約を取るまでが勝負」ですが、人材派遣はスタッフの管理や労務対応の比重が高いです。アウトソーシングはプロジェクト運営に近く、マネジメント能力が求められます。
応募前に事業形態を見極めることで「営業なのに労務管理がメインだった」といったミスマッチを防げます。求人票に「事業内容」や「契約形態」が曖昧に書かれている場合は、必ず面接や説明会で確認しましょう。
転職エージェント経由でしか得られない内部情報の活用
転職サイトの求人票だけでは分からない情報は多く存在します。
たとえば「上司のマネジメントスタイル」「インセンティブの実際の支給額」「過去の離職理由」などは、転職エージェント(人材紹介会社)を通じて初めて得られるケースが少なくありません。
転職エージェントは企業との取引実績や過去の紹介データを持っているため、内部事情を把握していることが多いです。

人材業界の隠れホワイト企業の探し方
「人材業界=ブラック」というイメージは強いですが、実際には働きやすい環境を整え、社員の定着率も高い“隠れホワイト企業”も存在します。
転職活動では、表面的な求人票やランキングだけで判断せず、複数の視点から企業を見極めることが大切です。ここでは、隠れホワイト企業を見つけるための具体的なポイントを紹介します。
離職率が低く社歴の長いコンサルタントが多い企業
人材業界は離職率が高いことで有名ですが、そんな中で「退職率」が低い企業は注目すべきです。
特にキャリアアドバイザーや営業職の定着率が高い会社は、労働環境が比較的安定している可能性が高いといえます。
定着率が高いということは、無理なノルマや過剰な残業が少なく、社員が腰を据えて働ける環境を整えているサインでもあります。

- ビズリーチ
転職エージェントと求職者をつなぐプラットフォーム - doda
顧客満足度No.1!国内最大級の転職サイト兼転職エージェント - マイナビジョブ20’s
20代・第二新卒専門の転職エージェント
大手・知名度が高い社名・サービスを持つ企業
大手や知名度の高いサービスを運営する企業はホワイトな可能性が高い傾向があります。
理由はシンプルで「売りやすい」からです。人材業界では、企業から求人を獲得する営業活動と、求職者への提案が日常業務となりますが、有名ブランドや認知度のあるサービスを提供している会社であれば、商談がスムーズに進みやすく、社員への営業負担も軽減されます。
結果として、働く社員のストレスも少なく、長期的に定着する人が多い環境が整いやすいのです。
急成長している会社(上場前後のベンチャー企業など)
急成長中の企業に身を置くことは、働きがいを感じやすくホワイト要素につながるケースがあります。
特に上場前後のベンチャー企業は組織が拡大していくフェーズにあり、制度の整備や人員補強が進むため、社員一人ひとりに過度な負担がかかりにくくなります。
また、事業成長を体感できることで「働いていて面白い」と感じやすく、モチベーションの維持にもつながります。もちろんベンチャー特有の忙しさはありますが、成長を実感できる分、前向きに働ける環境が整っていることも多いのです。

リファラル採用や自社メディアを持つ企業はブラック率が低い傾向
社員紹介(リファラル採用)を積極的に取り入れている会社は、社員からの評判が悪ければそもそも紹介が成り立ちません。
そのため、社内の満足度が高く、ブラック体質が少ない傾向にあります。また、自社で採用メディアやオウンドメディアを運営している企業は、情報発信に力を入れているため透明性が高く、労働環境に自信を持っているケースが多いです。
ランキングや口コミは参考程度にとどめるべき
転職サイトのランキングやや口コミサイトの評判はあくまで参考材料にしかなりません。
ランキング上位に入っているからといって必ずしもホワイト企業とは限らず、反対に掲載されていない企業の中にも隠れた優良企業が存在します。
また、口コミサイトに投稿される情報は「退職者によるネガティブな声」や「現役社員によるポジティブな声」に偏ることが多く、必ずしも実態を正確に反映しているとは言い難いのが現実です。匿名投稿である以上、個人的な主観や一時的な感情が強く出てしまうケースもあります。

- ビズリーチ
転職エージェントと求職者をつなぐプラットフォーム - doda
顧客満足度No.1!国内最大級の転職サイト兼転職エージェント - マイナビジョブ20’s
20代・第二新卒専門の転職エージェント
新卒入社と中途入社でのリスクの違い
人材業界は「やめとけ」と言われがちですが、新卒入社する場合と、中途入社として挑戦する場合ではリスクの種類が異なります。
それぞれの立場で想定されるメリット・デメリットを理解しておくことで、自分にとって最適なキャリア判断がしやすくなります。
新卒は「教育・育成」を受けやすいが離職率が高い
新卒採用で人材業界に入ると、社会人としての基礎を学びやすい環境があります。
クライアント対応は、コミュニケーション力・ヒアリング力・交渉力を鍛える絶好の機会です。営業力を磨くには適したスタート地点といえるでしょう。ただし、離職率が高い業界であるため、早期に辞めてしまう人も多く、「新卒カードを無駄にした」と後悔するリスクがあります。
長時間労働やノルマに適応できなければ、短期間でキャリアが中断される可能性も否定できません。

転職者は即戦力を求められるため、成果プレッシャーが強い
中途入社として人材業界に入る場合、即戦力としての成果が強く求められます。
特に法人営業や数字管理の経験がある人は高く評価される一方で、結果を出せなければ短期間で退職を迫られるケースもあります。
そのため、転職者にとっては「短期で成果を上げるスピード感」と「目標数字を達成し続ける持久力」が大きなプレッシャーとなります。
キャリアアップ狙いか、つなぎの転職かでリスクが変わる
人材業界への転職は「将来的にマネジメント経験を積んでキャリアアップしたい」という目的であれば、成果主義の環境は大きな成長機会になるでしょう。
一方で「とりあえず転職先を見つけたい」「つなぎで働きたい」という気持ちで入社すると、厳しい環境に耐えられず早期退職するリスクが高まります。
目的意識を明確にしたうえで挑戦しなければ、キャリアに傷が残る可能性もあるため注意が必要です。
まとめ|転職活動で人材業界を選ぶかどうかの判断基準
人材業界は確かに厳しい面があり、安易に選ぶと「やめとけばよかった」と後悔する可能性もあります。
しかし、自分の適性を理解し、ホワイトな企業を見極めることができれば、短期間で大きく成長し市場価値を高められる業界でもあります。
転職活動では「やめとけ」という声を鵜呑みにせず、複数の企業を比較しながらキャリアの可能性を冷静に判断しましょう。


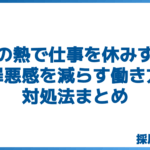

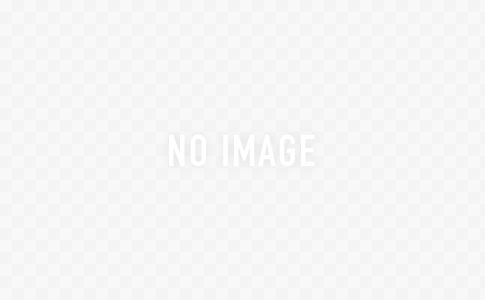






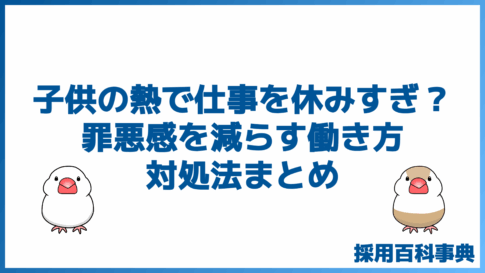

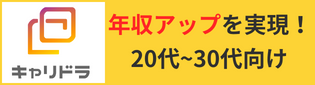


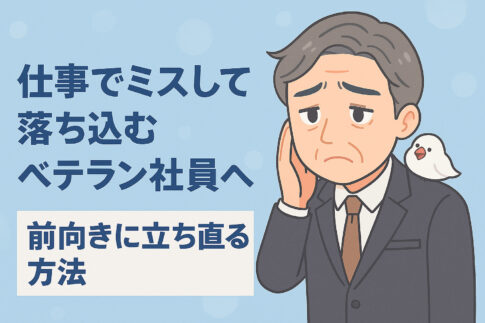
転職エージェントと求職者をつなぐプラットフォーム
顧客満足度No.1!国内最大級の転職サイト兼転職エージェント
20代・第二新卒専門の転職エージェント